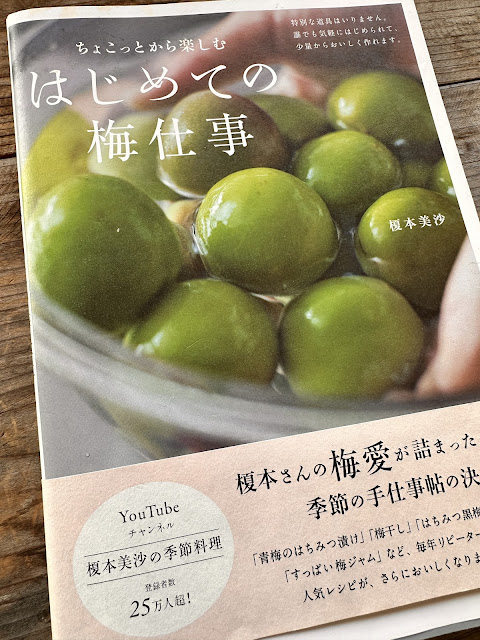普段の会話で滅多に耳にすることもなくなった懐かしい茨城弁に最近連続して接して妙に嬉しくなってしまった。しかもまだ若い40代がごく自然に会話の中で使用したのだから余計にだ。彼も口にした後に「あっ、今は使わないですね、(意味は)通じましたか?」と聞いてきたくらいだからやはり年配者の使う言葉と意識はしているのだろう。(あるいは小生が年上であることを考えて敢えて使って言ってみたのかも知れぬ。そうだとするとその心根が嬉しい。それに彼がもし家庭内でも普通に使っているとしたら、お子様たちは間違いなく伝承者となりうる。素晴らしい・・・。)
その言葉とは「ぐし」。標準語にすれば「〜ごと」であろうか。たとえば次の様に使うのが一般的だ。
【茨城弁】
A.シャインマスカットは皮ぐし食べれっぺよ。
B.(個々別々ではなくて)箱ぐし貰えっけ?
【標準語】
A.シャインマスカットは皮ごと食べられるでしょう。
B.(個々別々ではなくて箱に入ったまんま)箱ごと貰えますか?
と言った具合だ。
ちなみに「ぐし」のぐ(gu)は鼻濁音ぽいguで、かなり中途半端な発音。非鼻濁音と鼻濁音の中間くらいの感じで使っている。どちらとも取れるかなり高度な発音と言える。フランス語的な感じのものだ。説明すると小難しいが、茨城弁ネイティブスピーカーはそんなことは全く意識することなくちゃんと発音する(←ただこれはあくまで小生の考え)。
今後10年もしたら、斯様な古い茨城弁を使う人間も、聞いて理解する人間も激減するはずで、リアルに「死語」や「古語」になってしまうのではないかしらん。
 |
| 猛暑日が続き、早くもミソハギが咲き出した |